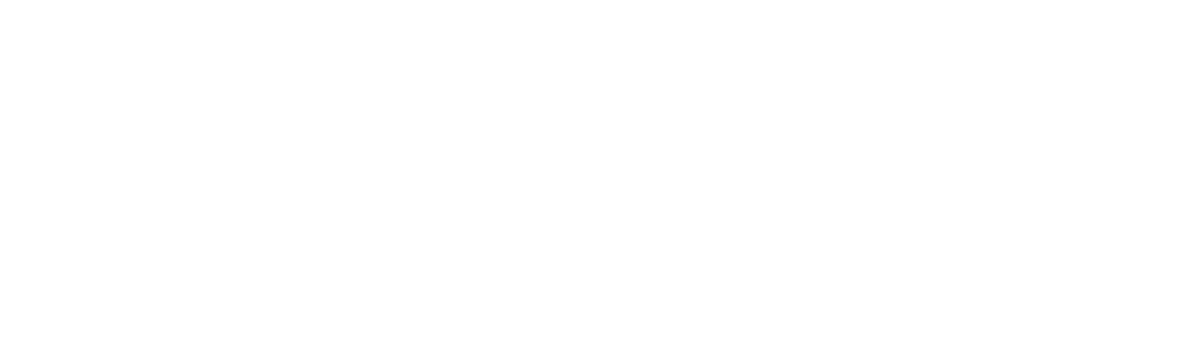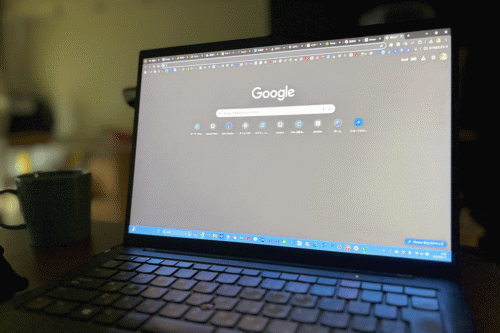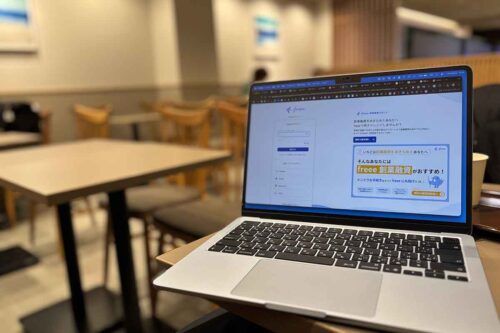※JR北広島駅にて – by Canon RP (RF35mm f 2.0 1/80 ISO 100)
仕事でなにかを伝える、説明するという場面はけっこうあります。
伝えるスキルは、磨いておいても損はしないはずです。
伝え方1つでそのあとも変わる
仕事で、やり方を教える、数字を見ながら説明することがあります。
「何かを伝える」という場面です。
・月次などの数字を見ながら
・決算資料を見ながら
・決算で気をつけたいポイントの説明
・改善策の説明
・いただく質問に対する回答
といったような場面です。
直接「伝える」こと自体が仕事とは言えなくても、大きい枠でいえば伝えることも仕事です。
「伝える」が仕事であれば、聞き手に伝わること、理解してもらえることが必要になります。
では、どうすれば伝わるのか、理解してもらえるのか。
正直、いろいろな考え方があるテーマですし、ズバッと一刀両断できるような回答もむずかしいところですが、あえて1つシンプルに挙げるとすると、”ざっくり伝える”ことだと考えています。
「正確性」と「網羅性」とは捨てていい
知っていること、人より詳しいことを伝えようとすると、つい詳細に語りたくなってしまいます。
細かい点まで説明しておけば、それだけ内容も正確に伝えやすいですし、「あのとき伝えているから」と安心できるかもしません。
ただ、正確性と網羅性にこだわるほど、聞き手にとっては、混乱のタネにもなってしまう”諸刃の剣”です。
伝わりやすいと考えて0から10まで伝えたとしても、聞き手が正確に10まで理解できているとは限らないものです。
たとえば会計や税金の計算をするというのなら、たしかに正確性と網羅性は必要なことかもしれません。
ただ、数字を1円単位で伝える必要があるかといえば、そうとも言えません。
「利益は5,357,252円(ごひゃくさんじゅうごまんにひゃくごじゅうにえん)ですから…」と正確に伝えようとすると、その分、話はクドくなりますし、結局「いくらだっけ?」と印象に残りにくくなります。
貸借対照表(BS)でも、現預金から繰越利益剰余金までのすべての科目の動きを伝えなくても、とくに増減の大きなポイントに絞ったほうが、伝わりやすいはずです。
聞き手の表情を伺いつつ、どこまで説明するべきか、どこを端折るか、聞き手の状況に応じて柔軟にコントロールできるかも、伝える側のスキルが問われる場面でもあります。
もちろん、専門用語が多すぎる、略語が多すぎる、早口すぎる、相づちが多すぎる(なさすぎる)というのは、伝わりやすさを考えて、配慮することも必要でしょう。
「伝える」には「伝わっている」が必要
「伝える」には、相手側に「伝わっている」必要があるという関係性があります。
相手の内面がわからない以上、ここがむずかしいところでもあるわけですが。
ただ、伝える側としてできることはあるでしょう。
「どうすれば伝わる確率をあげることができるか?」という視点です。
たとえば、言葉を使った「ざっくり」の説明にイメージ図を付け加えてみる方法も1つでしょう。
・数字のことを伝える場面はグラフを
・条件分岐のある流れを伝える場面はフロー図を
・箇条書き
・1枚のパワポの文字数は少なめにする
・色やフォントで強弱をつける
といったことで、口頭の「ざっくり」にイメージを補足することはできます。
耳だけでなく、目(視覚)にも伝えるようにしておくと、印象に残りやすいはずです。
伝えるスキルとしての「話す」と「書く」こと。どちらもざっくり加減は意識してスキルを磨いていきたいものです。
■編集後記
昨日は引き続き妻の実家。朝のタスクや習慣、とある研究を少し。夕方に札幌へ戻りました。
東京では桜が満開になったと聞きましたが、こちらは朝に降っていた雨がやがて、みじれ→雪→ホワイトアウトと一瞬で雪景色に逆戻りに。ただ、帰る頃には雪も解けていたので助かりました。
■昨日の1日1新
・幽遊白書(実写版)
・とある問い合わせ
■息子(11歳)
昨日は春休み4日目。引き続き、ばあばの家。朝5時に起きで、たっぷり遊んで過ごしました。
昼寝もせずずっと遊びっぱなし…。よほど誕生日プレゼントが気に入ったようで。