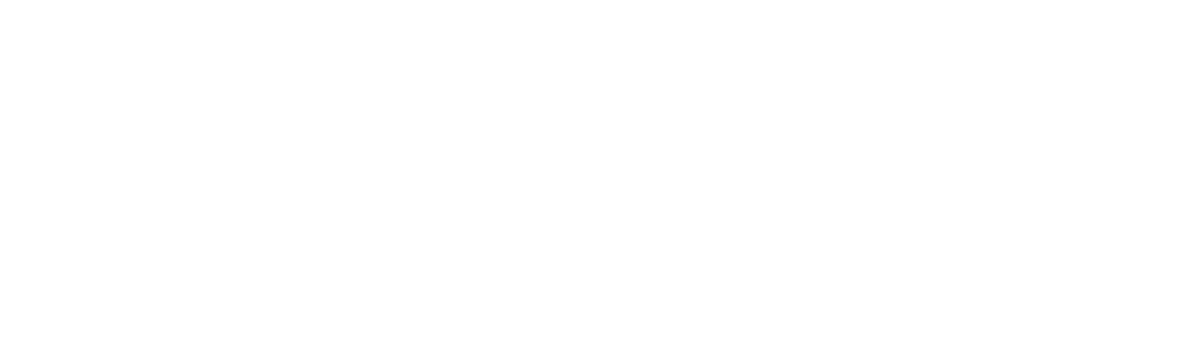今日で4日目の投稿。なんとか3日坊主は避けられました。。
今日は内部統制監査。お客様(会社)へ訪問しました。
会社(上場企業)では「うち(会社)の決算書は、ルールに従ってちゃんと作られたものですよ」ということを投資家に公表する義務があり、公認会計士の監査を受けなければなりません。この監査を内部統制監査と呼んでいます。
これは、アメリカで起きたエンロン事件(不正発覚)をきっかけに日本においても法制化され、日本版SOX法などとも呼ばれています。
内部統制監査とハンコの関係
そもそも内部統制監査ってナニ?についてです。
たとえば、会社が消耗品を買ったとします。
この場合、
・購入先から請求書が届く
↓
・請求書から伝票を起票する
↓
・上司がチェックする
という流れになるでしょう(大ざっぱに)。
この流れ。どういう取引かによっても様々なわけですが、会社の定めたルールどおりに処理しなければなりません(通常は)。
そしてこの「ルールどおりに経理されているか」をチェックするのが内部統制監査なわけです。
ただ、会社がそれなりの規模になれば伝票(仕訳)だけでも相当なボリューム。
年間で100万件の伝票があったとして、そのすべてを監査することはほぼ不可能です。
そこで、監査する側としてはその膨大な量の取引からサンプルを選ぶわけです。
そのサンプルを会社に提示し、資料を準備してもらいチェックすることになります。
そしてサンプルについてルールどおりに処理されていれば、確率論をよりどころとして100万件すべて大丈夫だろうと判断することになるわけです(たとえ話としてよくあるのが「どこを切っても金太郎飴になっているか」と言われたりしますが)。
脱ハンコはハードルが高い
前述の例は 請求書→会計伝票 というシンプルなものですが、
上司がチェックした証拠をどう残すのかを考えると、必ずしもハンコで残す必要はないでしょう。
クラウドサービスを利用した電子承認も以前に比べ普及しています。
ルールをこのようなルールとしてしまえばいいわけです。
ハンコを残すことはあくまで上司がチェックした証拠をどう残すかというお話です。
仮にハンコを残すルールになっているのなら、そのルールを疑ってみるできでしょう。「昔からやっているから…」、「今(コロナ後であっても)のご時世に照らしてどうなの?」という視点でルール自体も見直していくことも必要です。
・上司が不在だからハンコがもらえない(整理できない)
・ハンコをもらったのに書類が行方不明
・書類の保管場所に悩む
というように、”ハンコありき”であるがゆえに、非効率な仕事が脈々と続いているということも多々あります。
プリントアウトする手間も、コピー用紙を補充する、トナーの交換なども時間はかかるわけですから。
社内だけで済むものであれば、ルールを変えれば脱ハンコも不可能ではないはずです。
いっぽうで外部が関わっているという理由が脱ハンコを難しくしているということもあるでしょう。
・ハンコがないと・・・
・角印でないと・・・
・カラー印刷じゃないと・・・
取引先などの外部から望まれれば、そのとおりにするしかないと考えるケースも。
ただ、生活環境を一変させた出来事から3年。世の中の常識は3年前と比べて大きく変わりました。
・通勤しない
・リモートワーク
・ペーパーレス
・クラウド
・電子申請
などなど。
数年前までは目新しかったことが今はそうではありません(3年前に戻ったというケースも中にはありますが…)。
こういった世の中の変化で経験できたことを活かさないのはもったいないことでもあります。
過去の慣習とやらを変えるにしても、大義名分はつけやすいはずです。
脱ハンコ(ペーパーレスも)についてもあてはまることです。
【家事日記】
クイックルワイパーで床を。
ベッドメイキングを少々、夜は夕食準備(Uber eatsではま寿司)、食器洗い
【育児日記】
夕食のお寿司を食べやすい大きさにカット。
大好物のマグロを8貫食べてお腹ぽっこり。
今日は定期的な通院日で、売店でブラックサンダーのお土産をくれました
(明日のおやつにします)。
【本日の甘いもの】
御座候のおやき(赤あん)
【1日1新】
X-Mind